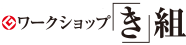ブログ
2020年11月23日 Mon
エッセイ:「石場建て」の真実
最近、古民家に見られる「石場建て」を再現する大工職人や設計者が増えています。
古民家によく見られる「石場建て」は免震性能があるということで注目されているのでしょう。その事自体は素晴らしいことだと思います。
しかし、伝統構法の本来の造り方を正確に理解しないと、一過性のブームに終わってしまう危険性があります。
伝統構法を標榜する多くの職人も、明治維新による西欧化が始まる以前の日本建築への理解が足りないように思います。
ここに、日本建築が近代化する過程において、いかに西欧建築の影響を受け、日本古来の伝統構法が分断されたのかを論考した本があります。
源愛日児著「木造軸組工法の近代化」(中央公論美術出版2009年)です。(書評添付)
この本には、現在の日本の一般的な家づくりである「在来工法」が明治以降西欧の技術を取り入れた「和洋折衷」であり、日本の伝統的な部材が失われ、多くの西欧的部材に置き換えられ衰退していったかが明確に示してあります。
まず、江戸時代には二階建ての家屋がほとんどなく「胴差」はなかったこと、明治になって二階建ての学校や庁舎が建てられることになり、下見板を貼る下地の間柱を止めるために横材として胴差が必要となったこと。さらに地震国日本の重要な耐震要素であった「貫」が「間柱」や「胴差」と「土台」を結ぶ「筋違」によって壁の中から追いやられ後退したこと。
日本建築が「減衰設計」を基本にしており「貫」のめり込み強さによるレジリエンス(復元力)を持ったしなやかで粘り強い構造であったことがこの本によってわかります。
その中で「石場建て」が地震国日本の重要な免震要素であったことも想像がつきます。
日本の建物は、自然の猛威に対して力で抵抗する「強度設計」ではなく「柳に風」で地震力や風の力をいなしていたのです。
その場合、建物は変形はしてもある程度の力に耐え、損傷限界の前にそれ以上力が入力しない仕組みを持っていたのです。
そこで「石場立て」の石の上を滑る「足元フリー」が重要になるのです。
その際に最も注意しなければならないのが、石の上においた柱がバラバラに動いて足元が開いて建物が崩れないようにすることです。
ですから石場建ての礎石は柱の足元にあることが重要なのです。さらに柱同士は「足固め」という横材で強固に結ばれていなければなりません。現在の在来工法のように、3尺おきの束はありません。
さらに上部の柱と梁同士も強固に結びついて一体化する必要があります。
そこで古民家を見ると、床下には「足固め」や「大引」と呼ばれる大きな横材があり、柱頭では「折置組」という「柱と梁と桁の三部材が一体化」した丈夫な木組みになっています。
地震や台風等の大きな力が加わるとそれらの部材は、一斉に同じ方向に動いて建物が滑り、免震的に働くのです。
ここで留意しなければいけないのが、束の存在です。足元がムカデのように何本もの束によって支えられていては、建物が一体に動くことは困難で傾いた束が床を持ち上げて建物が滑ってくれません。
在来工法になれた現代の大工や設計者には、ここが最も気づかない盲点となります。
また、「強度設計」の建物は「許容応力度計算」によって耐震性を計算しますが、「減衰設計」の場合は「限界耐力計算」によって粘り強さを確認します。
国土交通省によって2011年に兵庫県の防災センターで行われた足元フリーの実大実験の結果も、ムカデの足ように並んだ多くの束が、建物が滑る邪魔をして、隅柱をくじいてしまいました。
また、胴差が通し柱を折ってしまうこともわかりました。筋違も梁を持ち上げて、胴差を折り、一階が倒壊します。
明治以降に二階建て庁舎や学校の建物を作るために挿入された胴差しは、地震時に通し柱を折る悪さをするのです。
熊本地震では、続けて起きた二度の大きな波に、強い筋違が胴差を突き上げて建物を崩壊に導くような事例もあり、当時の国の構造設計担当者の間でも、筋違の是非が問われたと聞いています。
古民家の架構を免震の観点から見れば明らかな事実も、明治以来、和洋の工法が混在したままの状態で現在まで推移しているのが混乱を生んでいます。
ここで一度立ち止まって「伝統構法の定義」を明確にし、次の世代に引き継げる構法として進化を図るべきだと考えます。
変形を許容しても「生存空間」を作る「貫・足固め・折置組」による「減衰設計」を選択するならば、伝統構法の継承を形だけの模倣に終わらず、真実を伝承する科学的かつ人間的知見を持ちたいところです。
そのためには、2008年から行われた国交省の実大実験による検証をさらに進めてほしいと思います。